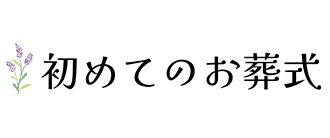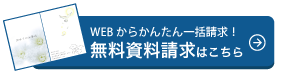生前準備とは?元気な時に葬儀を考える大切さ【喪主・ご遺族向け】

生前の葬儀準備とは、自らの死後の手続きや内容について、事前に計画することです。
「生前に葬儀の準備なんて縁起が悪い」と思われる方もいることでしょう。
自分の死のことなんて普通なら考えたくないものです。
ではなぜ、生前に葬儀の準備をする必要があるのでしょうか。
本記事では生前準備のメリットやデメリット、具体的なやり方まで詳しく解説します。
なぜ生前葬儀の準備が必要なのか?

生前の葬儀準備は、大切な家族人々のため、そして自らの希望を伝えるためです。突然の死により、家族は多くの手続きや出費などに直面します。
自分の葬儀を準備するなんて縁起が悪いと感じますが、事前に計画をしておくことで、家族の精神的・経済的なストレスを緩和できます。さらに、自らの希望を明確にしておくことで、いざという時に家族が葬儀のやり方に迷うことなく、希望通りに執り行うことができます。
生前に葬儀準備をするメリット
生前の葬儀準備には以下のメリットがあります。
- 家族への負担軽減
- 経済的な安心
- 本人の希望に沿った葬儀ができる
家族への負担軽減
大切な家族が亡くなった悲しみの最中に葬儀社を選び、葬儀の内容、段取りなど、家族の負担は大きく、メンタルへの負荷も心配です。生前に葬儀の詳細を決めておくことで、家族の精神的な負担を減らすことができます。
経済的な安心
葬儀の費用は一般的には平均100〜300万程度となります。葬儀でお金のことは考えたくないものですが、突然の出費は家族への経済的負担が大きいのが現実です。
生前に葬儀の種類を「家族葬」や「一般葬」など、ご家族の財政事情を知ったうえで計画しておくことで、家族への費用の負担を減らせます。
本人の希望に沿った葬儀ができる
生前の葬儀準備は、ご自身が「どんな葬儀の形式」で「どんな人達を呼びたい」など、意志や希望をしっかりと伝えることができます。
葬儀が自分の希望に沿ったものとなり、家族や親しい人々にとってもも本人の意志を尊重した葬儀を行えます。また、参列に来られる親しい方へ最後のメッセージ、感謝の気持ちをきちんと自分の言葉で伝えることができます。
生前に葬儀準備をするデメリット
生前の葬儀準備は、死に関する繊細な内容ですので、以下のようなデメリットも考えられます。
- 縁起が悪いと感じる
- 感情的な負担
縁起が悪いと感じる
生前に葬儀の準備をすることを縁起が悪いと感じられやすいです。文化的・宗教的な背景から、一部の人々は生前の葬儀準備に抵抗を感じることがあります。また、周囲からの反対も考えられます。
感情的な負担
生前に自分の死や葬儀について向き合う必要があり、具体的に考えることは、感情的に重く、ストレスを感じることがあります。人によって性格は違いますが、精神的に弱い方には生前の葬儀準備は不向きと言えます。
生前の葬儀準備のステップ
生前の葬儀準備は以下のステップで進めることが重要です。
- 意識の生理
- 葬儀社に相談・選定
- 葬儀内容の決定
- 葬儀の宗教
- 葬儀費用の準備
- 葬儀保険への加入
- 互助会への加入
- 連絡先リストの作成
- 遺族や親族とのコミュニケーション
意識の整理
生前葬儀の準備を始める前に、まずは自分の心の中にある感情や考えを整理することです。
人は自らの終焉について考えることを避けがちですが、葬儀の生前準備をするうえでは大切です。
また、葬儀の準備だけでなく、自分の人生観や価値観についても深く考える機会となります。自分のこれまでの人生や家族への想い、そして死後の希望をしっかりと認識できます。
葬儀社に相談・選定
感情の整理ができたら、まずは葬儀社に相談し、自身の希望や考えを伝えましょう。葬儀社は経験が豊富ですので、多くのケースやニーズに合わせて考えてくれます。信頼のおける葬儀社を選ぶことで、安心して生前の葬儀準備を進められます。
葬儀内容の決定
葬儀は大きなセレモニーホールで挙げる「一般葬」や、親族だけで行う「家族葬」などの形式があります。葬儀の規模は親しい友人や知人、親族の数で変わります。周囲の状況や希望に合わせて、葬儀の規模、場所などの基本的な内容を決めましょう。
葬儀の宗教
葬儀は基本的に本人が信仰している宗教・宗派で行います。日本は主に仏教葬が多いですが、キリスト教や神道などもあり、宗派によっても儀式のスタイルは異なります。
稀に家族の中で信仰宗教や宗派が違う場合がありますが、基本的には故人の信仰宗教を尊重するのが一般的です。
葬儀費用の準備
葬儀にはそれなりの費用がかかります。生前に見積もりを取ることで、具体的な費用のイメージを持つことができ、ご予算に合わせた葬儀のスタイルを選べます。生前に葬儀の費用を準備しておくことで、家族への経済的な負担を減らせます。
注意すべき点として、預金名義人が亡くなった場合、銀行の口座は一時的に凍結されます。現金を引き出すには、遺産相続権を持つ遺族の賛同が必要です。
ただし、2019年7月に法が改正され、これまでは遺産相続権を持つすべての賛同がないと、払い戻しができなかったのですが、1人でも賛同があれば、単独で一部払い戻しが可能となっています。
払い戻し額については以下の通りです。
相続開始時の預貯金債権額✖️1/3=単独で払い戻せる額
※ただし、1 つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円まで。
葬儀保険への加入
葬儀保険とは、葬儀のための保険です。医師の診断も必要なく小額から加入できます。ご契約者が亡くなった場合、死亡診断書などの書類を提出することで、翌営業日には保険金が支払われます。
ただし、少額保険保険には保険の責任期間があります。たとえば、葬儀保険に加入し、1ヶ月間の支払いのみで亡くなった場合は保険対象外となるため、一定期間の保険料支払いが必要です。
保険の支払い条件については、葬儀保険の各社ホームページよりご確認ください。
互助会への加入
互助会とは、「冠婚葬祭互助会」という呼び名が正式名称で、結婚式や葬儀のための積立です。互助会に加入すると指定の葬儀会場で特別割引などの特典があります。
ただし、決まった場所や葬儀プランから選ぶことになり、自由度が低いデメリットがあります。また、積立金のみでは葬儀費用をカバーするのが難しく、追加費用が必要となる場合が多いです。
「家族の為にとにかく葬儀の費用負担を減らしたい」という方にはおすすめですが、「自分の思い描いた葬儀を行いたい」という方には、向いていないサービスです。
遺影撮影
遺影は、葬儀や法事などの際に使用される写真です。そのため、遺影撮影は葬儀の準備の中でも重要です。遺影は故人の最後の姿を家族や親しい人々に伝えるものであり、その写真一枚に多くの思いや想い出が詰まっています。
遺影撮影は、生前に専門のスタジオや写真家に依頼して行うことが一般的です。自然な表情や好きな服装、背景を選ぶことができ、故人の魅力や人柄を最もよく伝えることができます。
また、撮影の際には、故人が生前に好んでいたアイテムや趣味の道具を持参することで、より思い出深い遺影とすることも可能できます。事前の準備や計画をしっかりと行うことをおすすめします。
連絡先リストの作成
葬儀の際には多くの人々に連絡を取る必要があります。突然のことで連絡先が見つけられなかったり、大切な人に連絡ができなかったりするのは避けたいです。
生前に「誰を呼びたいか」の連絡先リストを作成しておくことで、ご家族が迅速に連絡を取ることができ、自分にとって大切な人を漏れなく葬儀に呼ぶことができます。
故人と親交の深かった人たちが参列することで、家族にとってもより意義のある葬儀となるでしょう。
遺族や親族とのコミュニケーション
生前の葬儀準備を進める際は、家族や親しい人々とのコミュニケーションがとても大切です。家族や親しい人への相談を欠かさず行い、お互いで共通の理解、思いやりを持って進めましょう。
自身の希望や考えをしっかりと伝え、家族や親しい人の意見や希望も取り入れることで、心に残る特別な葬儀が実現できるでしょう。
葬儀の希望はエンディングノートにまとめるのがおすすめ
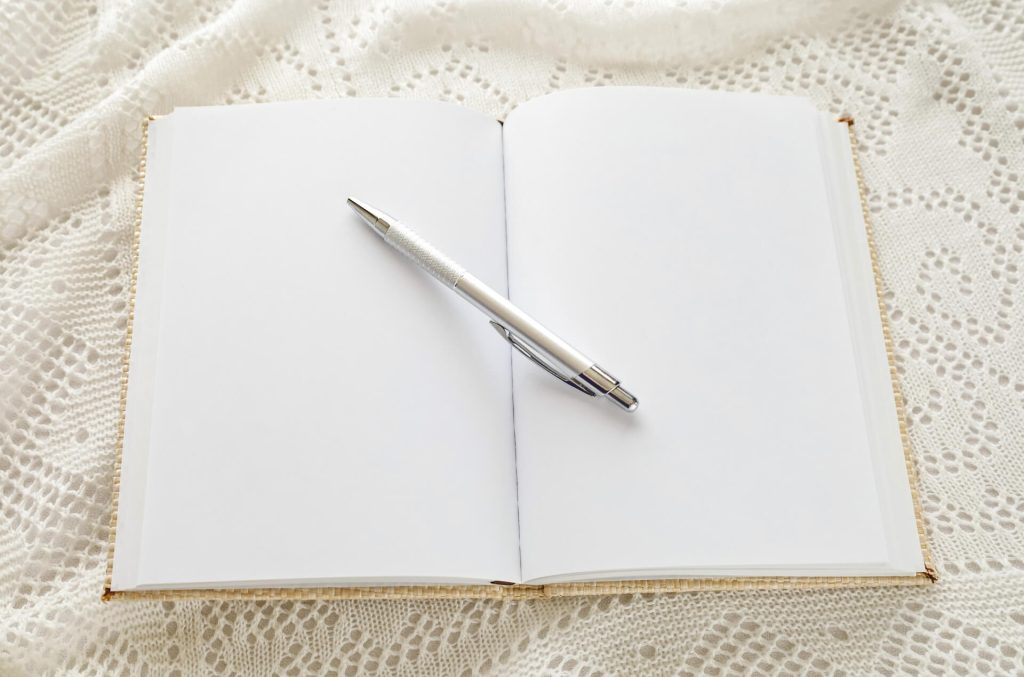
葬儀の希望はエンディングノートにまとめることをおすすめします。エンディングノートとは、自身の死後の希望を生前に書き記しておくノートです。
これまでの人生を振り返りながら、家族へのメッセージ、死後に伝えて欲しい友人の連絡先、口座情報や保険、葬儀の形式やお墓などがあります。
ノートにまとめておくことで、故人が「どんな人と親交が深かったのか」を明確に把握でき、残された家族が誰との親交を重要視するべきか判断しやすいです。
その他、知っておきたい情報も整理されているので、いざという時に役立ちます。
まとめ:生前の葬儀準備は家族を思う最後の贈り物

生前の葬儀準備は、家族への愛情を形にした最後の手紙のようなものです。ただの準備や手続きではなく、家族への感謝や思いやりの気持ちが込められています。
生前の葬儀の準備の意義と方法をよく理解し、愛する家族のために一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。