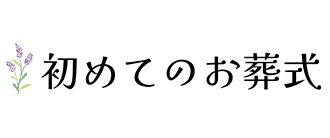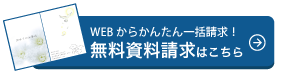法事とは?法要の種類と時期、準備からマナーまで解説します

法事や法要は、葬儀後に故人を偲び、その冥福を祈る大切な仏教の儀式です。
しかし、初めて葬儀後の法事や法要を検討される方は「何から始めれば良いのか」「どのような準備が必要なのか」など、疑問や不安が多いのではないでしょうか。
本記事では、法事と法要の基本的な知識から、種類と時期、準備の方法、当日の流れ、そして適切なマナーまで解説します。これから法事や法要を検討される方は、ぜひ参考にご一読ください。
法事とは
法事とは法要から会食までの全般行事のことを言います。初七日から七回忌、四十九日など、故人が亡くなってから一定期間ごとに儀式が行われます。法事には、遺族や親族、生前に故人のつながりの深かった知人、友人が集まり、故人を偲ぶ時間です。
また、法事は故人への供養の意味合いが強く、遺族の心の癒しや、故人との絆を再確認する機会ともなります。法事には、四十九日法要、一周忌、三回忌など、故人が亡くなってからの期間に応じた様々な種類があり、それぞれに意味や目的があります。
法事と法要の違いは?
法事と法要はよく混同されがちですが、明確な違いがあります。
法事は、故人の冥福を祈るために行われる一連の行事全体を指し、法要、会食、懇親会などを含む広い意味を持ちます。一方、法要は、僧侶による読経や焼香など、故人の供養を目的とした仏教儀式の一部を指します。
法要の種類
法要の主なものには、初七日、四十九日、開眼法要、納骨法要、一周忌、三回忌などがあり、それぞれに意味と目的があります。それぞれ、詳しく解説します。
初七日(しょなぬか)
初七日(しょなぬか)は、故人が亡くなってから7日目に行われる法要です。この期間は、故人の魂があの世とこの世の間をさまよっているとされ、遺族が初めて故人のために行う供養の儀式となります。この法要を通じて、故人の新たな旅立ちを祈る意味が込められています。
四十九日
四十九日法要は、故人が亡くなってから49日目に行われる法要となります。仏教では七日ごとに極楽浄土へ行けるかの裁判が行われ、最終判断が49日にあたります。故人の魂が六道の輪廻から解放され、成仏できるかが決まる重要な法要です。
この日は、遺族や親族、友人が集まり、故人が極楽浄土に無事に辿り着けるように祈ります。
開眼法要
開眼法要は、新しいお墓を建てた場合に僧侶が読経し、故人の魂を宿らせる儀式となります。
納骨法要
納骨法要は、故人の遺骨をお墓や納骨堂に納める際に行われる法要です。納骨式の時期に決まりはありませんが、四十九日や一周忌の法要と合わせて行われます。
一周忌
一周忌は、故人が亡くなってから1年後の命日に行われる法要です。四十九日の法要は忌明けの節目となりますが、一周忌は最も長い喪が明ける節目であり、重要な意味があります。
この法要は、故人を偲び、その冥福を祈るためのもので、遺族や親族、故人と親しかった人々が多く集まります。
三回忌
三回忌は、故人が亡くなってから満2年目の命日に行われる法要で、故人の冥福を改めて祈るための行事です。
「2年目になぜ三回忌?」と思われる方も多いですが、年忌法要では満1年の一周忌が過ぎた後は、亡くなった日を1回目の命日と数えるからです。ですので、2年目が3回目の命日隣、三回忌となります。
法事で準備すること
法事を行うにあたり、会場選びや日時の決定など、事前に計画的に行うことで、スムーズな法事を進行できます。それぞれ、詳しく解説します。
会場選び
法事の会場選びは、故人との関係性や遺族の意向、参列者の数などを考慮して決めます。自宅、寺院、公共の集会所、ホテルの宴会場などが選択肢になりますが、アクセスの良さや会場の設備、雰囲気も重要なポイントです。
自宅で行う場合は、家族だけの小規模な法事に適していますが、大人数を招く場合は、寺院やホテルの宴会場を利用すると便利です。会場を選ぶ際は、事前に下見をして、必要な設備が整っているか確認しましょう。
日時決め
法事の日時を決める際は、故人の命日に合わせるのが一般的ですが、遠方から参列する人がいる場合や、平日である場合は、週末にずらすことも検討しましょう。
週末にずらす場合は、命日より前の土日に一周忌法要を行うことが一般的で、「前倒しはできるが、後ろ倒しはしてはならない。」とされています。
また、僧侶のスケジュールも考慮に入れる必要があります。日時を決めたら、速やかに関係者に連絡を取り、スケジュールを調整しましょう。
案内状を送る
法事の日時と会場が決まったら、案内状を作成し、参列を予定している親族や友人に送ります。案内状には、法事の日時、会場、故人の名前、連絡先などを明記し、返信を求める場合は返信用はがきを同封すると良いでしょう。案内状は法事の1ヶ月前までには発送することが望ましいです。デザインや文面にも心を込めて、故人を偲ぶ気持ちを伝えましょう。
会食の手配
法事後の会食は、故人を偲びながら親族や友人が交流を深める大切な時間です。会食の規模や形式は、法事の性質や参列者の数によって異なります。
料理は和食が一般的ですが、参列者の好みや予算に応じて選びましょう。会場がホテルや料亭の場合は、事前にメニューを確認し、アレルギー対応やベジタリアンメニューが必要な場合は相談しておくと良いです。会食の手配は早めに行い、当日の流れも確認しておきましょう。
引き出物の購入
法事に参列してくれた人への感謝の気持ちを込めて引き出物を用意します。引き出物は、故人との思い出や遺族の感謝の気持ちを形にしたもので、食品やタオルなどの実用的な品が選ばれることが多いです。
購入する際は、包装やのし紙にも気を配りましょう。引き出物は法事の1~2週間前には準備を完了させ、当日スムーズに配布できるようにしておきましょう。
法事の流れ
法事は一般的に以下の流れで執り行われます。
- 開式の挨拶
- 僧侶による読経
- 焼香(遺族、親族、参列者が順に行う)
- 僧侶による法話
- 閉式の挨拶
- 会食
- 解散
法事のお坊さんの相場
法事を執り行う際には、お坊さんに読経していただくことが一般的ですが、そのお布施の相場は地域や宗派、法事の規模によって異なります。
一般的に、初七日や四十九日などの小規模な法要では、3万円から5万円程度が相場とされ、一周忌や三回忌など、より大きな法事では、5万円から10万円程度が目安になることが多いです。
ただし、あくまで一般的な相場であり、お坊さんとの関係性や、法事にかける想い、地域の慣習によって変動することがあります。
また、お布施は故人への供養とお坊さんへの感謝の気持ちを表すものであるため、無理のない範囲で心を込めて準備することが大切です。事前に寺院や僧侶と相談し、適切な金額を確認しておくと安心です。
法事のマナー
法事におけるマナーは、故人への敬意と遺族への配慮を示すために重要です。適切な服装選びや数珠の持参、挨拶など、丁寧な行動などが求められます。
法事の服装
法事に参列する際の服装は、一般的には葬儀と同じで喪服となります。喪服がない場合は、男性は黒や紺などのダークスーツに白いシャツ、無地のネクタイを選びます。
女性は、黒や紺、グレーなどの控えめな色のワンピースやスーツが適しています。足元は、清潔感のある靴を選び、女性は高すぎるヒールは避けるのが無難です。派手な色や柄、過度なアクセサリーは避け、地味で落ち着いた装いを心がけましょう。
法事での供物
法事では、故人への供養として供物を捧げることが一般的です。供物には、故人が生前好んでいた食べ物や飲み物、花や果物などが選ばれます。これらの供物は、故人の冥福を祈り、故人が次の世界で苦しむことがないようにとの願いを込めて捧げられます。
供物は、法要が始まる前に遺族や僧侶の指示に従って適切な場所に丁寧に設置します。供物を選ぶ際には、故人の好みや宗教的な意味合いを考慮することが大切です。
法事での御供物料
御供物料とは法事に招かれた場合に包むお金で、相場は5千円〜一万円程度となります。表書きには「御仏前」と書いて準備をしましょう。
法事での挨拶
法事における挨拶は、遺族が参列者に対して感謝を述べます。挨拶は簡潔かつ心を込めて行うことが大切です。
法事・法要の意味を理解しておきましょう
法事や法要は、故人を偲び、冥福を祈るための大切な儀式です。一定期間ごとに行われる法事にはそれぞれ意味があり、重要な役割があります。
親族や友人、知人が集まり、生前の故人を話しながら、温かみのある法事を執り行うことで、故人もきっと喜ばれることでしょう。